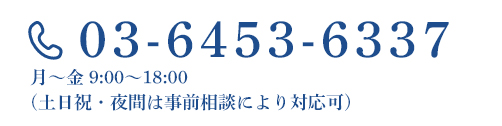現金以外の対価と顧客に支払われる対価
2021年10月18日
弁護士・公認会計士 片 山 智 裕
※本文中で引用,参照する会計基準書等の条項は,末尾の凡例に表示の略語で記載しています。
Step3-④ 現金以外の対価
企業は,Step3「取引価格を算定する」で,以下の順に処理を行います。
1 企業は,まず,顧客との契約に含まれる現金以外の対価を識別します。
企業が現金以外の対価を識別しない場合には,このサブ・ステップ(Step3–④現金以外の対価)は終了します。
2 契約において約束された対価が現金以外の対価である場合には,当該対価を時価により算定します(第59項)。企業が現金以外の対価を合理的に見積ることができない場合には,当該対価と交換に顧客に約束した財又はサービスの独立販売価格を基礎として当該対価を算定します(第60項)。
3 企業は,現金以外の対価の時価が変動する場合は変動対価の額を見積りますが,その見積りの変動の理由が,株価の変動等,対価の種類によるものだけではない場合(例えば,企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて時価が変動する場合)には,変動対価の見積りの制限(第54項)を適用します(第61項)。
現金以外の対価の識別
l 現金以外の対価の識別
企業は,まず,顧客との契約に含まれる現金以外の対価を識別します。
現金以外の対価には,例えば,株式その他の金融資産,有形固定資産,企業による契約の履行に資するための財又はサービス(材料,設備又は労働)などがあります。
l 企業による契約の履行に資するための財又はサービス
企業による契約の履行に資するために,顧客が財又はサービス(例えば,材料,設備又は労働)を企業に提供する場合には,企業は,顧客から提供された財又はサービスを支配するかどうかを判定します(第62項)。
企業が顧客から提供された財又はサービスを支配する場合には,当該財又はサービスを,顧客から受け取る現金以外の対価として処理します(第62項)。
したがって,企業は,契約において約束された現金対価の額に,顧客から提供された財又はサービスの時価を加算して取引価格を算定し,契約における履行義務に配分します。
これに対し,企業が顧客から提供された財又はサービスを支配しない場合には,当該財又はサービスは依然として顧客が支配しているので,取引価格に含めません。
取引価格の算定
l 現金以外の対価の時価
企業は,契約において約束された対価が現金以外の場合,取引価格を算定するにあたって,当該対価を時価により算定する(第59項)。
企業は,顧客から現金を受け取る場合には,企業に流入する資産の価値すなわち受け取る現金の額で取引価格を算定するので,これと整合させるため,企業が顧客から現金以外の対価を受け取る場合にも,企業に流入する資産の価値すなわち現金以外の対価の時価で取引価格を算定します(IFRS/BC 248)。
l 現金以外の対価の時価を合理的に見積ることができない場合
企業は,現金以外の対価の時価を合理的に見積ることができない場合には,当該対価と交換に顧客に約束した財又はサービスの独立販売価格を基礎として当該対価を算定します(第60項)。
企業に流入する資産と交換に流出する資産の価値の方が高い信頼性をもって見積ることができる場合には,その価値を基礎として間接的に企業に流入する資産の価値を測定することは,他の会計基準(例えば,IFRS第2号「株式に基づく報酬」)と整合的です(IFRS/BC 249)。
変動対価の見積りの制限
l 現金以外の対価の変動性
現金以外の対価の時価の見積りは,企業が現金で受け取る変動対価と同様に変動する可能性がありますが,その変動性には,次のa又はbの両方があります(IFRS/BC 250,251)。
a 将来の事象の発生又は不発生によって変動する可能性
現金以外の対価の受け取りに条件が付されている場合(例えば,対価である株式を受け取る企業の権利が将来の事象の発生又は不発生に係る場合)。
b 現金以外の対価自体の価格又は価値の変動
現金以外の対価自体の価格又は価値が変動する場合(例えば,対価である株式の1株当たりの価格が変動する場合)。
l 変動対価の見積りの制限の適用
まず,企業は,現金以外の対価の時価が変動する場合には,変動対価の額を見積ります。
次に,企業は,現金以外の対価の時価の見積りが変動する理由が,株価の変動等,対価の種類によるものだけではない場合(例えば,企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて時価が変動する場合)には,変動対価の見積りの制限(第54項,指針25,26)を適用します(第61項)。
変動対価の見積りの制限は,受け取る対価の種類が現金かどうかを問わず,企業の履行に関連する同種の不確実性に適用すべきです。例えば,顧客の業績に基づく割増として顧客の株式を受け取る企業の権利の時価の見積りは,株式自体の価格又は価値の変動(上記b)だけでなく,株式を受け取るかどうかの不確実性(上記a)にも関連します。本基準は,このように現金以外の対価の時価の見積りが変動する理由が,企業の履行に関連する不確実性にもある場合(上記aを含む場合)には,現金以外の対価の時価の見積りにあたって,変動対価の見積りの制限を適用することとします(IFRS/BC 252)。
Step3-⑤ 顧客に支払われる対価
企業は,Step3「取引価格を算定する」で,以下の順に処理を行います。
1 企業は,まず,顧客との契約に含まれる顧客に支払われる対価を識別します。
顧客に支払われる対価とは,企業が顧客(あるいは顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者)に対して支払う又は支払うと見込まれる対価をいいます(第63項)。
企業は,顧客との契約において,顧客に支払われる対価を,顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われる対価(あるいは両者の組み合わせ)と区分して識別します。
企業が顧客に支払われる対価を識別しない場合には,このサブ・ステップ(Step3–⑤顧客に支払われる対価)は終了します。
2 企業は,顧客に支払われる対価を識別した場合には,顧客に支払われる対価の額を算定します(第63項)。
顧客に支払われる対価に変動対価が含まれる場合には,変動対価の見積り(変動対価の見積りの制限を含みます。第50項~第54項)を適用します(第63項)。
3 企業は,次のa又はbのいずれか遅い方が発生した時点で,認識する又は認識した収益から顧客に支払われる対価の額を減額します(第64項)。
a 関連する財又はサービスの移転に対する収益を認識する時
b 企業が対価を支払うか又は支払を約束する時
顧客に支払われる対価の識別
l 顧客に支払われる対価
顧客に支払われる対価とは,企業が顧客(あるいは顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者)に対して支払う又は支払うと見込まれる対価をいいます(第63項)。
顧客に支払われる対価の形態には,現金(キャッシュ・バック)のほか,企業に対する債務額に充当できるクレジットその他のもの(例えば,クーポンやバウチャー)も含まれます(第63項,IFRS第70項)。
Ø 顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者に支払われる対価
顧客に支払われる対価には,企業が顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者に対して支払う又は支払うと見込まれる対価も含まれます(第145項)。
例えば,メーカーである企業が小売業者に製品を販売するとともに,消費者に割引クーポンを発行します。小売業者は,企業の製品の販売にあたって,消費者から割引クーポンの提示を受けたときは,代金を値引きするとともに,回収した割引クーポンを企業に提出し,消費者に値引きした金額を企業に補償してもらいます。このように,企業は,顧客(小売業者)に対し,消費者が企業の製品の購入にあたって提示した割引クーポンを回収して企業に提出することを条件に,消費者に値引きした金額を補償することを約束します。この場合の対価の形態は割引クーポンすなわち顧客にとって「企業に対する債務額に充当できるクーポン」であり,企業にとっては「顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者」に間接的に支払う対価に該当します。
l 顧客に支払われる対価の識別
企業が顧客(あるいは顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者)に対して対価を支払う又は支払うと見込まれる場合,その対価は,①約束した財又はサービスと交換に顧客から受領する対価の減額(値引き・返金),②顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払う対価又は③両者の組合せによる場合があります(IFRS/BC 255)。
企業は,顧客に対して支払う又は支払うと見込まれる対価が,以下のa~cのいずれかを判定し,顧客に支払われる対価を識別します。
a 約束した財又はサービスと交換に顧客から受領する対価の減額(値引き・返金)
当該対価は,顧客との契約に基づき約束した財又はサービス(企業の財又はサービス)と交換に顧客から受領する対価の減額であり,企業は,顧客に支払われる対価を識別し,その額を取引価格から減額します(第63項)。
b 顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払う対価
当該対価は,顧客との契約とは別に,当該顧客から別個の財又はサービス(顧客の財又はサービス)を仕入れる(購入する)契約に基づき支払う対価であり,企業は,当該財又はサービスを仕入先からの購入と同様の方法で処理します(指針30,IFRS第71項)。
c aとbの組合せ
顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払う対価(上記bの対価)が当該財又はサービスの時価を超える場合には,企業は,当該超過額を取引価格(顧客との契約に基づき顧客から受領する対価の額)から減額します。
顧客から受領する別個の財又はサービスの時価を合理的に見積ることができない場合には,当該財又はサービスと交換に支払う対価の全額を取引価格から減額します(指針30,IFRS第71項)。
企業が約束した財又はサービスと交換に顧客から受領する対価の額と,当該顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払う対価の額は,たとえそれらが別々の取引であっても関連することがあります。例えば,顧客は,企業から提供を受ける企業の財又はサービスに対し,もし企業に提供する顧客の財又はサービスと交換に企業から対価を受け取らない場合に支払ったであろう金額よりも多額の対価を支払う場合があります。そのような場合には,収益を忠実に描写するため,企業が受領する別個の財又はサービスと交換に支払う対価として処理する金額は,当該財又はサービスの時価に限定し,時価を超過する金額があれば取引価格(顧客との契約に基づく顧客から受領する対価の額)を減額すべきです(IFRS/BC 257)。
l 顧客から受領する別個の財又はサービス
上記bにより仕入先からの購入と同様の方法で処理するのは,企業が受領する財又はサービス(顧客の財又はサービス)が,顧客との契約において約束した財又はサービス(企業の財又はサービス)とは別個のものである場合(第34項参照)に限ります(IFRS/BC 256)。
例えば,企業が顧客である販売業者に製品を販売するとともに,顧客から製品陳列サービス(製品の在庫保管・展示・サポート等)の提供を受け,当該サービスに対して対価を支払う場合(設例23),企業は,製品陳列サービスから単独で便益を享受することができませんが,企業が容易に利用できる他の資源(企業が取り扱う製品)と組み合わせて便益を享受することができます(第34項(1)参照)。そこで,企業は,顧客から受領する製品陳列サービスが,顧客との契約において約束した製品とは別個のものであると判定し,顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払う対価として,仕入先からの購入と同様の方法で処理します。もし,顧客に支払う対価が製品陳列サービスの時価を超える場合には,企業は,その超過額を顧客との契約(製品の販売)の取引価格から減額します。
逆に,企業が顧客である販売業者に製品を販売するとともに,顧客が製品を収容するために棚に変更を加える費用を補償する場合(設例14),企業は,棚について何らかの権利を支配しないため,顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払う対価に該当せず,補償の全額を顧客との契約(製品の販売)の取引価格から減額します。
顧客に支払われる対価の額の算定
企業は,顧客に支払われる対価を識別した場合には,顧客に支払われる対価の額を算定します(第63項)。
l 変動対価の見積り
顧客に支払われる対価に変動対価が含まれる場合には,変動対価の見積り(変動対価の見積りの制限を含みます。第50項~第54項)を適用します(第63項)。
まず,企業は,変動対価の額を見積ります(第50項~第53項)。
本基準は,実際には企業が未だ対価を顧客に支払っていなくとも,その支払を約束する時に収益から減額することを明確にします(第64項(2)参照)。そのため,企業は,顧客に対価の支払を約束する時点では,顧客に支払われる対価が将来の事象の発生又は不発生を条件として変動する可能性がある場合が少なくありません。例えば,企業が,顧客が所定の数を購入することを条件に対価の支払を約束した時点では,顧客がその条件を達成するかどうかの不確実性のために顧客に支払われる対価に変動する可能性のある部分が含まれます。そこで,企業は,その不確実性を反映して顧客に支払われる対価の額を見積り,収益から減額します(IFRS/BC 258)。
l 変動対価の見積りの制限
次に,企業は,顧客に支払われる対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に,解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り,取引価格に含めます(第54項)。
企業が顧客に対価を支払うかどうかの不確実性が高すぎる場合には,取引価格から減額すべき顧客に支払われる対価の額が低く見積られるため,計上した収益の重大な戻入れが生じるおそれがあります。そこで,企業は,顧客に支払われる対価を減額した後の取引価格を制限する(すなわち顧客に支払われる対価の額を高く見積もる)必要があります。
取引価格の減額
顧客に支払われる対価を取引価額から減額する場合には,企業は,次のa又はbのいずれか遅い方が発生した時点で(又は発生するにつれて),収益を減額します(第64項)。
a 関連する財又はサービスの移転に対する収益を認識する時
b 企業が対価を支払うか又は支払を約束する時
企業が対価を支払う約束は,企業の取引慣行に基づく場合もあります。
顧客に支払われる対価を取引価額から減額する場合には,企業は,Step5「履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する」で,関連した履行義務を充足した時に収益を減額して認識します。また,企業が履行義務を充足して収益を認識した後になってはじめて顧客に対価を支払うか又は支払を約束する場合には,既に認識した収益を直ちに減額します。
【凡例】 第〇項 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
指針〇 同適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
設例〇 同適用指針設例
IFRS第〇項 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
IFRS/BC IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(結論の根拠)